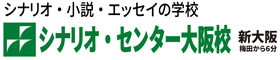しるし 作:植田尚美
道が細く伸びている。辺りは真っ白で明るい。目がつぶれそうな程だ。眩しくて目を閉じると、瞼の裏から闇が染み出て広がる。そのまま歩き続けていると、どこからか微かに声が聞こえた。はっとして目を開ける。目の中には闇が残るようだ。
足音が聞こえる。いつの間にかぴったりと寄り添うように。少し後ろからずっとついてくる。
見るとすぐ横に男がいた。息を吐(つ)けばかかるほどだ。だれだか確かめようとするけれど、うまくいかない。やがて男の歩みが少し速くなった。
「覚えてる?」男がようやくこちらに顔を向けて言った。左目の下の大きな黒子。わたしはすぐに分ったが黙っていた。すると男はさらにべったり寄り添うようについてくる。
わたしが黙ったまま歩き続けていると、焦れたのか今度は男は先を歩きはじめた。道はこの一本だけで、わたしはその後を行くしかない。辺りは日が落ちはじめて、空が青黒くなっていくようだった。
男は足を止めてわたしを見た。広がる闇のせいか青黒い顔をしている。唇はいっそう濃く青く、菖蒲の花弁を思わせた。男はけっしてこちらから目を離そうとせず、わたしの頭の中を覗くように見つめている。
道の先が次第に細くなり、ふっと切れている。闇の中を這うように一本の細く赤い川がそこを横切っている。突然、男が膝から崩れ落ち倒れた。自分でも気付かず支えようと腕をのばした瞬間、息を呑み思わず後ずさった。心臓の辺りがべったりと血に染まっていた。
「なに驚いてるの? お前がやったんだろ」男が言った。かすかに微笑んでいる。逃げ出そうとしたその時、背後から腕が巻き付いて首を締め上げられた。死にものぐるいで腕から逃れようとするが、硬くてほどけない。
「ぼくの金は?」
「あっちの男に」息も切れぎれに答えた。
「全部?」わたしは黙っている。
「どうして?」
「……あっちの男のがいいから」
そう言えば男が傷つくことは分っていた。一瞬、男の腕から力が抜けた。わたしは肉を食いちぎらんばかりに噛み付き逃れた。舌に残る錆びた鉛の味。男の左手の内側に真っ赤な血が噴き出している。
「待ってろ、必ず」男は倒れた。目は大きく見開いて動かない。けれど微かに微笑んでいつまでもわたしを見つめていた。
目の前の糸のような赤い川を、すがるような思いで踏み越え、わたしは目が覚めた。
あの男を殺したのはもう一年も前なのに、刺した手応えが残っている。夢の中で噛んだ肉の感触もそのままで、思わず口をぬぐった。
傍らで男が寝息をたてている。わたしが選んだ男だ。どうしてこっちを選んだのかよく分らない。もう終ったことだ。眠る男に口づけて、わたしは自分の大きく膨らんだ腹をなでた。
幾度も激痛に耐え、そしてまた息んだ。これが最後だった。体中の力が抜け、赤ん坊の激しい泣き声が聞こえた。清潔な白い布に包まれた新しい生命にほっとしたのも束の間だった。真っ白な産着を覗いた瞬間、全身総毛立った。激しく泣く赤ん坊の左目の下には大きな黒子があり、小さな花弁のように開いた左の掌には赤黒い歯形が残っていた。気付くと赤ん坊は静かに微笑んでいた。 (終)