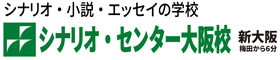最後の朝のプロポーズ 作:濱田コオ
君のいない人生なんて考えられない。
君がいない世界なんて俺にとっては死と同じだ。それが夫のプロポーズだった。
あれから50年後の夫が目の前にいる。
私は夫をじっと見つめた。
皺とシミだらけの垂れ下がった皮膚。
ところどころから飛び出し、その役割を忘れてしまった白い毛髪。
それらはもう夫のものではなく、枯れた山やひび割れた大地のように見え、その中に私がひとり、目的もなく彷徨っているように思える。
「おい、君、何を見ている。うちの家内はどうした!」
私は、私がこの男の妻であることをすべての言い訳にして、その言い訳だけに従い、それ以上深く考えることをやめたのはもう随分前のことだ。この男の妻であるという一点だけで、私は私の犠牲から身を守っている。だが、一番前に置いた偽(にせ)の意識だけに従うことは、死を意味していた。
「君、聞いてるのか?」
今朝のテーブルには夫が大好きな食事のメニューが並んでいる。
豚の生姜焼き。ブリの照り焼き。辛いカレーライス。ねぎの入った納豆。薄いビーフカツ。甘いたまごやき。キムチ鍋。そしてハンバーグ。昨夜は一睡もせずに、徹夜でこれらの食事を拵えた。
「それに君、この朝食はなんなんだ? お手伝いじゃ話にならん。うちのやつはどこにいった。うちの家内を呼びたまえ」
君のいない人生なんて考えられない。
君がいない世界なんて俺にとっては死と同じだ。
君のいない人生なんて考えられない。
君がいない世界なんて俺にとっては死と同じだ。
「何をぶつぶつ言っている。家内は! 家内はどこなんだ!」
「あなたの言う通りにしてあげる」
私は包丁を手に取り、夫を刺した。
「君、何をする!」
何度も何度も、包丁を刺した。
枯れた山が赤く咲いて、ひび割れた大地が赤く濡れた。血のしぶきが、テーブルの上の料理に降りかかる。
私の顎から滴るのは、汗ではなく真っ赤な血だ。
蝉の声が聞こえてきた。
テレビからは笑い声が聞こえてくる。
カーテンをあけると、夏の真っ白な光が台所を支配して、その光の中に、赤くて小さい夫の姿が消えていった。
君のいない人生なんて考えられない。
君がいない世界なんて俺にとっては死と同じだ。
私は、私の返事もまた、覚えている。
あなたのいない人生なんて、私にとっても死と同じ。
偽の意識だけに従うことは、死を意味している。でも偽の意識だけに従っていると、それが本当になってしまう。
また、蝉の声がやんだ。
了