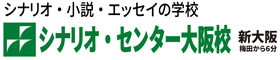邪視 作:堀内円
曲がりくねった細い山道は、生い茂る野草と巨大杉のせいで、真昼でも薄暗かった。
雲行きが怪しいな。前田は軽自動車のハンドルを握りなおした。視界が悪く、時速は十キロほどしか出せない。遠くで雷が唸りだし、フロントガラスに大きな雨粒が落ちてきた。
俺、ついてないわ。前田はため息をついた。
さっきまで気分は上上だった。高校時代の恩師が、集中豪雨に遭ったと聞き、土日を利用して支援物資を届けに出向いた。恩師はもちろん村の人々にも感謝され、英雄気取りで帰路についた。清々しい思いに浸りながら。
どうせ俺は天に嫌われている。来月いっぱいでリストラされるのもそのせいだわ。何が「まだ三十三だろ。どうにでもなる」だ。勝手に俺の人生狂わせやがって。いいわ、どんどん降れよ雨でも矢でも。
腹が減っているのもあって、前田はヤケをおこした。何か食べれば機嫌はおさまりそうだった。だがコンビニはもちろん、周囲には露店の一つもない。村からの道中も廃墟しかなく、飲食店が連なる国道に出るには、山を二つ越えねばならない。カーナビは、国道への到着を二時間後と表示している。
はぁ、二時間はないわ。腹減りすぎだろ。
ワイパーが動くたび、前田の舌打ちが響く。ニ十分程して、やっと道が開けだした。
路肩に人影が見える。割烹着を着た、肉づきの良い中年の女だった。小雨の中、傘をささずに白い小型犬を抱えている。近くの住人なのか、衣服はそれほど濡れていなかった。
追い越し様、前田は女に声をかけた。
「すみません、この辺りで食事のできる所は」
女は右側を指した。道先の分岐点に古びた看板が立っている。文字は雨風で剥げていて、【不定休】【天然素材】しか読み取れない。
ラッキー、このおばさんが営んでる店だわ。
前田はわき道に車を止め、女の方へ寄った。
女は微笑んだ。慣れた笑みだった。
「この子は可哀想に、もう目が見えんのんよ」
何の前触れもなく、女が口走った。
マルチーズだろうか。目元は毛に覆われていてよく解らない。前田は、犬よりも、こんな山奥に住む冴えない中年女が、全ての指に高価な金や宝石の指輪をし、何重にも金の首飾りや腕輪をしているのに驚いた。かと思えば背中には、九つの目が描かれた妙なモノをぶらさげている。カニの甲羅に見えなくもない。
「スッポンの甲羅やわ、それ」見透かしたように、女が言った。
前田は気味が悪くなり、車に戻ろうかと思った。だが、空腹の上、都会で見かける田舎蕎麦屋に似た家屋と、畑にできている野菜や井戸を見ると気が変わり、女の後につづいた。
店は三席カウンターがあるだけだった。壁の棚には瓶詰めの保存食が沢山並んでいる。山菜、木の実の蜂蜜漬け、酢大豆に酢ごぼう。
前田は嬉しくなった。素朴ながらに手が込んでいる。良いことをしたからだろうか。やっぱ天は俺の味方だわ。と、前田は思った。
山の幸の瓶詰め以外にも、年季の入った茶色い壺が並ぶ棚があった。ぬか漬けや手作り味噌に違いない。前田の期待は膨らんだ。
女はカウンターの中に入ると、指輪をすべて外し、流し台の隅へ無造作に置いた。
「ここら辺って、廃墟ばっかっスよね」
「みんな居らんようになった。トウビョウモチもオサキモチも、みんな絶えてしもうた」女はあたりまえのように答えた。
「は? なんスかそれ、ナンとかモチって」
「ええ歳して知らんとはな。代々ツキモノ持っとる家のことよ、まぁ、ツキモノ筋言うたらイヌガミが有名やわな。嫉妬や恨みで人に憑りついて酷い悪さする、あのツキモノよ」
唖然とする前田を尻目に、女はつづけた。
「トウビョウ言うたらミミズ位の蛇でな。それに憑かれたら呪い殺される。かなわんから、ほれ、これ邪視言うて、魔よけつけとるんよ」
女は、スッポンの甲羅に描かれた九つの目を見せると、黄色い歯を見せて笑った。
タイミングよく前田の腹が大きく鳴った。女は「ふっ」と、低い声を出すと、錆びた収穫バサミを持って畑へと向かった。
あんな奇妙な話、興味ないわ。と、前田は思った。目の前には、女の外した指輪が転がっている。手を伸ばせば届く距離だ。
一つ盗んでやろうか。女に指輪の行方を聞かれても、シラを切り通して車に乗れば楽勝、余裕で逃げ切れる。それなら二つでも大丈夫だろう。「今、はずみで落して」とか言って、女が探している間にダッシュするのも有りだわ。それなら三つ、いや、全部いけそうだわ。
前田が指輪に手を伸ばした時だった。いつの間にか背後に女が立っていた。即座に前田は手を引っ込めようとしたが、女が前田の後ろ髪を鷲掴みにする方がはやかった。前田は「違うんです」と言いたかったが、乾いた喉音が鳴っているにすぎなかった。すぐに金属製の尖った何かの先端が、前田の視界に入るやいなや、背筋から足先に冷たい痺れが走った。ほぼ同時に、感じたことのない強烈な熱さが目元を襲ってきた。
やめろ、目が燃える。
数秒後。前田は、土間でのた打ち回る自分と同じ服を着た白髪の男を見た。両目を押さえた手先がぴくぴくしている。水晶体が映しているのは、まぎれもない前田自身だった。
次に見えたのは、収穫バサミを持つ女の手と小ぶりの茶色い漬物壷だった。女は、血のついたハサミの刃先で、壷の丸い蓋を開けた。
急に視界が暗くなった。そう長くない時を経て、徐々に暗闇の中の視界が広がった。
半透明の球が蠢いている。殆どが黒で、茶、灰色、少量だが青と緑もいる。小指の爪位の大きさで、我先にと向かってきた。
「ジャシ様よぉ、喜んでもうとりますか。ほうですか、犬の眼とは違いますか。新入りのしろまなこ食うたら、またちぃと我慢して下されや。ジャシ様絶やすわけにはいかんしな」
女の言葉は、土間で息絶えた前田にも、まなこだらけの壷にも届かなかった。