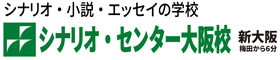俳句の季語は奇語ばかり? 6
子規三題―「生身魂」「砧」「糸瓜の水取る」 秋の季語
明治は遠くなりにけり、で日本の近代文学に多大な影響を及ぼした正岡子規(1867~1902年)の秋の季語で詠まれた三句を紹介する。
子規は雅号で、本名は常規(つねのり)という。「子規」はホトトギスの異名で、結核を病んでいた常規は、血を吐くまで鳴くというホトトギスに自分の身の上を重ね合わせ、子規と名乗った。既述の高浜虚子は、俳句における子規の後継者にあたる。
「生身魂(いきみたま)」とは、年長者を敬い、ご馳走する盆行事のひとつ。また、敬われる年長者自身をいう。では、年長者とは何歳のことなのか? 「生身魂七十と申し達者なり」と子規は言っている。
「砧(きぬた)」は、植物繊維で織った布を柔らかくするために、木槌で打つ作業のこと。あるいは、その木の打ち台のこと。「三千の遊女に砧うたせばや」スケールの大きい句だ。
次に「糸瓜」だ。糸瓜と書いて「へちま」と読む。「糸瓜の水取る(へちまのみずとる)」とは、糸瓜の茎の切口をビンに挿しておくと取れる水のこと。糸瓜の水は、去痰鎮咳薬(のどにからんだ痰を取り除き、咳を静める薬)や化粧水として用いられる。「をととひのへちまの水も取らざりき 痰一斗糸瓜の水も間に合はず」とは、正岡子規の辞世の句である。byメイ