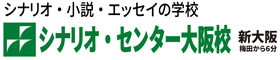俳句の季語は奇語ばかり? 5
蕪村三題―「落穂拾い」「薬掘る」「焼米」 秋の季語
現代では使われづらいが、漢字はそのまま読める秋の季語で詠まれた、与謝蕪村の句を三つ紹介する。
「落穂拾い(おちぼひろい)」「薬掘る(くすりほる)」「焼米(やきごめ)」がそれだ。
ミレーの名画「落穂拾い」を鑑賞すれば一目瞭然だが、「落穂拾い」とは、刈り取った稲穂が、こぼれているのを拾い作業を言う。機械化の今は、コンバインで刈り取るから、こんな光景は目にすることはない。「落穂拾い日あたるかたへ歩みゆく」、訳さなくてもスーッと意味も分かる。
「薬掘る」は、秋の山野に入って、薬草の根や茎を採取すること。秋は植物の葉が枯れて、根や茎に成分が集まってくる。薬草の根を掘ることになる。逆に春は葉が出始めるので、葉を摘むから「薬草摘み」が春の季語になっている。薬草堀は、優雅な作業かと思ったら、ちょっとコワ~イ句になっている。「草掘けふ蛇骨を得たり鳧(けり)」は誰にでも詠める句ではない。
「焼米」は、生米あるいは乾飯(かれいい)を炒めた食べ物。実際、生米で試してみたが、美味しくも何ともない。大歳時記には、食べ物に関する記述が散見されるが、料理法が載っていない。そこで蕪村の一句。「やき米や仏の膝にあまる迄」仏様は蕪村の焼き米を喜んで食したのだろうか?byメイ