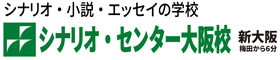「八百八橋にはドラマがある!」その37
~商人の町大阪にはこんな素敵な場所がいっぱい~
神事としての鉾流橋
鉾流しというと大阪の人でもすぐに思い浮かばないかもしれませんが、実は天神祭と言えばこの橋なのです。天神祭の宵宮に神鉾を川に流す行事「鉾流しの神事」にちなんで名づけられた橋でもあり、天満宮の鳥居もあって現在もこの場所で実施されています。
天神祭りと言えば日本の三大祭りの一であり、大阪三大夏祭りでもある由緒正しいお祭りです。なのでこの橋も江戸時代からの長い歴史がと思われますが、実は橋が架けられたのは大正7年で近代になってからのことです。大正時代に大阪控訴院や中央公会堂、大阪市庁舎の整備が進められる中で新しく架けられたのです。現在の橋には高欄や照明灯、親柱など日本調でクラシックなデザインが採用されており、天神祭の船渡御がイメージされるようなデザインになっています。

戦時下の鉾流橋
橋といえば架け替えはあるものの、長らく変わらないように思われがちです。しかし、実際には災害や戦時下でその姿形や役割を変えていることもあります。鉾流橋は昭和初期になって燈籠風の親柱や入母屋風の屋根の照明灯など鉾流神事と調和したデザインに変更されました。明治維新の混乱で中止されていた鉾流の神事もこの時の架橋に伴って復活しています。
そんな栄光もつかの間、今度は第二次世界大戦で金属供出を求められて撤去され、復元されることなく年月が過ぎていきます。やっと復活できたのは昭和55年になってからのことでした。いろんな時代を経ながら、大阪の橋として歴史を歩み続けてきたのです。

大阪の天神祭りの舞台として
天神祭りと歴史の長い祭りでもあり、多くの小説や映画の舞台にも取り上げられてきました。ただこの橋は近代になってからできたので、登場するドラマといえば朝の連続テレビ小説の「ごちそうさん」ではないでしょうか。大阪の天満界隈を舞台にした劇中では、夏の天神祭での出来事も描かれています。多くの人に親しまれ、水都大阪らしい祭りはこれからも愛されていくのでしょうね。