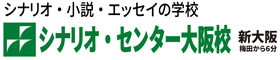「八百八橋にはドラマがある!」その36
~商人の町大阪にはこんな素敵な場所がいっぱい~
当時の面影を伝える樽屋橋
現在の大阪の町を形作ったのは、豊臣秀吉による大阪城築城と言われています。横堀川の掘削を始めとして、江戸時代を通じて多くの水路が整備されていった歴史があります。樽屋橋もその一つで、天満堀川に架けられた橋の一つでした。
現在では高速道路の下にひっそりと親柱が残されているだけですが、往時には中之島の北側に架けられた橋だけでも「太平橋」「菅原橋」「天神小橋」などこの辺りの人々の往来や水運などが発達していたことが古地図などの資料にも残されています。樽屋町は酒造やそれに伴う樽の製造など水を活かした町だったのです。

酒造が盛んだった樽屋町
天満の周辺は昔から水が良いとされていたそうで、大阪での油や酒造業が盛んな場所でした。酒屋は各戸に井戸を作ってくみ上げ、酒作りに励んでいました。天満の酒は灘に負けないとまで言われ、樽屋町の町名の由来も酒造業のための樽の製作が盛んだったからと言われています。
樽屋橋の架かる天満堀川は大川へのバイパスになっており、水路の要衝でもありました。しかし、昭和47年に高速道路建設に伴って埋められてしまいます。大阪での酒造業も時代の移り変わりによって消えてしまったのです。

樽屋おせん
酒造業の盛んだった樽屋町には、一つの有名な物語があります。それが井原西鶴の「好色五代女」で描かれた樽屋おせんです。この「おせんさん」は実在の人物で、この界隈で樽を作っていた職人の女房をモデルにしたと言われています。
今でいうスキャンダル話であり、当時の大阪でかなり有名だったそうです。近所に住む男に無理に言い寄られたという被害者の側面が強かった彼女の悲劇を、井原西鶴は「好色五代女」は創作で描きなおしています。土地勘があったとも言われており、事件の裏に何かを感じ取った西鶴ならではの作家の目があったのかもしれません。