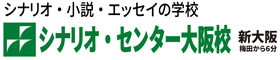見当違いの芭蕉俳句への旅 4
閑かさや 岩にしみ入る 蟬の声
ズバリ、何ゼミが鳴いているのか。斎藤茂吉(歌人)は、アブラゼミだと断言した。ところが、ニイ二イゼミとの反論が出た。
この句が詠まれたのは元禄2年5月27日、西暦1689年7月13日のこと。場所は、立石寺(山形県)だ。山中にある山寺で、切り立った絶壁には御堂が数多く建てられている。霊界にタイムスリップしそうな所だ。立石寺のある東北地方では、7月にアブラゼミは鳴いていない。いたってフィールドワーク的な指摘だ。
斎藤先生も誤りを認めて、現在の定説はニイ二イゼミになっている。アブラゼミは「ジージー」と鳴き、二イ二イゼミは「ジー」と鳴く。似てはいる。その二イ二イゼミの「ジー」がしきりに鳴いているのに、「閑かさや」というのだ。蟬の鳴き声だけで、他に音がしないから、「閑か」なのかも知れない。蟬の声は、岩にしみ入るのだから、「動(声)」と「静(岩)」が好対照になっている。
うがった見方をすれば、「生と死」の対比ともいえそうだ。詠まれた蟬が「二イ二イゼミ」で良かった。「ミンミンゼミ」だとミンミンと鳴くし、「ツクツクボウシ」だとツクツクボウシと鳴く。やかましい鳴き声だ。
気持ちを集中すると聞こえなくなる鳴き声を考えても、やはり「二イ二イゼミ」が一番似合っている。それにしても、芭蕉は不思議な世界観を持った歌人だ。byメイ