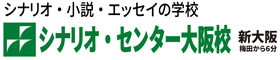俳句の季語は奇語ばかり? 7
「歯固」「水祝」―新年の季語にみる一茶の人生
「雀の子そこのけそこのけお馬が通る」「やれ打つな蠅が手をすり足をする」「やせ蛙負けるな一茶是にあり」誰もが諳んじている教科書に載った一茶の句だ。
俳人と言えば、芭蕉、蕪村、一茶とベスト3に名を連ねる一茶。作品数でも、芭蕉の1000、蕪村の3000を遥かに超える21200で、さもありなんと言うところだが、彼の人生は波乱万丈だったことはあまり知られていない。
信州柏原の農家に生まれ、3歳で母は没し、8歳で継母を迎える。15歳で江戸に出て丁稚奉公の後、世間の辛酸をなめ、52歳にして故郷にもどり一家をなすが、娶った妻の間に生まれた子供たちは次々と死に、妻にも先立たれ、再婚した妻とは離縁。家が火事に会い、焼け残った土蔵のなかでその生涯を終えている。
一茶は歯が悪く50歳前には、全ての歯を失っている。そんな一茶が詠んだ句が、「歯固の歯一枚もなかりけり」と「迯(にげ)しなや水祝るる五十聟(むこ)」だ。
「歯固(はがため)」は、正月三が日に歯を丈夫にする意味をこめて堅い餅などを食べた風習のことで、「水祝(みずいわい)」とは、前年に結婚した新婚夫婦に、ご祝儀として水を浴びせる行事のこと。
若ければ、寒中運動会のようなものだが、65歳で亡くなる50代の一茶にとっては、バツゲームのようなものだったろう。あるいは当人は、人生はそんなものと諦観していたのか。言葉が胸に響く一句である。byメイ