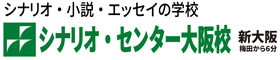なにわは、仏像の宝庫?! 3
三蔵法師の弟子のアイデアが生んだタイル状の仏さま
『西遊記』で有名な三蔵法師。彼のモデルとなったのが唐時代、シルクロードを通ってインドに渡った玄奘三蔵(602~645年)。
インドから経典や仏像を長安に持ち帰り、現在、ユネスコの文化遺産に指定されている大雁塔(652年~:中華人民共和国西安市の大慈恩寺にある7層64mの塔)に納めた。
ところで、仏像は経典と違い壊れやすい。移動させるのが難しい。そこで生まれたのが、粘土の型抜きのようにして造る「塼仏(せんぶつ)」と呼ばれる仏さまだ。この半立体的な仏像が、遣唐僧・道昭により日本に持ち帰られ、現在、奈良市の阿弥陀山寺などから出土されている。また、これを元に型を取って造られた塼仏が、大阪府交野市の獅子窟寺遺跡を始め、堺市の太平寺や滋賀県大津市の穴太廃寺や京都府大山崎町の山崎院跡などなにわの地から出土されている。
製造法を詳しくいうと、塼仏は、粘土を凹型につめて形成し、型から脱した後に、焼成して金泥や金箔で装飾してタイル状の仏像に仕上げるのだ。だから、塼仏は壊れにくく、情報伝達力が高い。しかもコピーを造りやすい利点があった。塼仏の正式名称は、「火頭形三尊塼仏」という。他の仏さまと異なる大きな特徴は、中央の如来様が椅子に座っている。如来が椅子に座る姿は、7~8世紀の仏像にしかほぼみられない形だ。byメイ