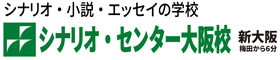「八百八橋にはドラマがある!」その28
~商人の町大阪にはこんな素敵な場所がいっぱい~
近代大阪を表していた端建蔵橋(はたてくらばし)
モダニズムとは20世紀初頭に生まれたムーブメントですが、この運動は日本においても現代芸術や生活に多大な影響を与えたと言われています。その象徴こそが端建蔵橋なのです。この橋から見る当時の川の南岸には住友倉庫の灰色の壁があり、北岸には中央卸売市場の白い壁が聳え立っていました。船によって次々と物が運び込まれる姿、発展が止まらない商都大阪を望める場所でもありました。
橋からは安治川筋の先にある海も見えるそうです。夕日の時間帯には絶景であったとのことですが・・・なんと撮影に行ったら工事中でした。2030年までは見られないとのこと残念です。

端建蔵橋の歴史
端建蔵橋は大阪市の土佐堀川に架かる橋です。江戸時代の中之島には諸藩の蔵屋敷が建ち並んでいて、その西端にあった蔵という意味で端建蔵という地名が生まれたとされています。
初代の橋は明治41年ですが、数度の架け替えを経て1921年の三代目は百年間も維持されていました。かつては市電も通っていたそうで、工事中にかつての線路が見つかったとかで話題になりました。2022年より架け替え工事が始まって間もなく四代目の予定です。令和になった今度はどんな橋になるのでしょうか。

映画「泥の河」の舞台に
太宰治賞を受賞した宮本輝の小説「泥の河」は、この端建蔵橋の界隈を舞台にした作品です。潮の香りが漂う港のような風情があり、水運が発達した大阪に暮らした少年が友人と出会って大人になっていく姿が描かれています。
橋から見える高い煙突群が吐き出す煙にまみれた都、東洋のマンチェスターと言われた大阪の景色が物語に色をなしています。しかし、実際の撮影は残念ながら大阪ではありません。行動成長期を経て当時の面影を残す場所が大阪ではすでになく、名古屋や撮影所で撮影が行われたのでした。