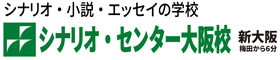見当違いの芭蕉俳句への旅 6
草いろいろ おのおの花の 手柄かな
この句を見ると、即、童謡「チューリップ」を思い出す。今では、小学校で童謡を教えないのだろうか?
それはさておき、チューリップの歌だ。「さいたさいたチューリップのはなが ならんだならんだ あか しろ きいろ どのはな みてもきれいだな」どの花の色もそれぞれきれいだと、江戸時代の芭蕉も、今の日本の子供達も思っているのである。これはスゴイことだ。
160年ほどの時を越えて、俳句が人々の心を打つことに、言葉の持つパワーは偉大だ……と言ったところで、花の話に戻る。きれいな花には虫が飛んできて、蜜を吸うときにからだにつけた花粉を次の同じ種類の花へと運んでくれる。それは花の色で決まる。ミツバチは紫色の花から花に飛び交う。だから、すべての花の色には意味があって、植物はさまざまな花の色を選択している。
それなら、チューリップには、なぜ様々な色があるのだろう? それは、人間が野生のチューリップを改良して、様々な花の色を創り出したからだ。人間の深層心理の中には「多様性は美しい」という思いが秘められていて、様々なフラワー・カラーを求めるようだ。
そのことを見抜いていた芭蕉は、花の色に優劣はなく、どの花の色もそれぞれにきれいだ、と詠っている。植物たちは、蜜と花粉の量を工夫して、ハチや他の虫を呼び寄せる。植物の「コスパ」は驚きだ。byメイ