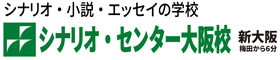俳句の季語は奇語ばかり? 3
「瓜番」「霍乱」「早苗饗」 夏の季語
「うりばん」、「かくらん」、「さなぶり」と読む。
「瓜番」とは、きゅうり、スイカなどが盗まれないように、畑に作った番小屋で番をすること。あるいは、その晩をする人のこと。
「霍乱」は、暑気あたり、食中毒によって起こる、吐いたり下したりする症状の総称。
「早苗饗」は、田植えを終え、田の神への感謝をささげ、田の神を送る祭りを言う。
読みづらい語だし、今どきは使わないワードだと思う。こんな季語で、俳句を詠む人がいるの?(いたの?)と思ったら、ズバリ、いたのだ。明治・大正・昭和の時代を生きた俳人、高浜虚子(1874~1959年)がその人だ。俳句文芸誌「ホトトギス」の主宰で、現在活字で確認できる句数だけでも2万2千句あるという。
「瓜番」からは、「先生が瓜盗人でおわせしか」、「霍乱」では、「霍乱にかからんかと思ひつつ歩く」、「早苗饗」は、「早苗饗や神棚遠く灯ともりぬ」と詠っている。
「早苗饗」は大歳時記では、神棚に洗い清めた早苗を供え農具を飾り、赤飯を焚き、餅をついたりして祝うとある。田植え機を使って1日で終わる田植えでは祝う意識は薄くなっているのではと思ってしまう。
「霍乱」は、今では急性胃腸カタルのこと。季語としてはイメージが暗い。
「瓜番」には、ちょっと驚かされた。今では、さしずめ、「先生が盗撮犯でおはせしか」となるのだろうか?byメイ