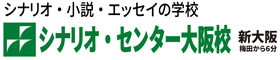万博のお茶と音楽 3
パリ万博は音楽万博
世界初の万博は、1851年のロンドン万博だが、その後はフランス・パリの万博が、万博史上を席捲している。1855年、1867年、1878年、1889年、1900年、1937年にパリ万博が開催されている。これらの万博は、技術革新の祭典というよりも、芸術の祭典であり、音楽の祭典と呼ぶにふさわしいものだった。
1867年の万博では、作曲コンクールが開催され、カンタータにカミーユ・サン=サーンスの作品が選ばれている。
エッフェル塔の建設で名高い1889年のパリ万博では、パリの五大オーケストラによるフランス音楽のコンサートが行われた。
1900年のパリ万博は、「19世紀の総決算」のテーマのもと、127の国際会議が開催され、宗教・政治を除く12部門で、8万人の参加者がさまざまな学術会議に出席した。万博音楽会議もその1つで、4日間にわたって、教育・楽器・書法と音楽実践など、様々なトピックが議論された。
1937年のパリ万博では開催期間中に、現在も活動している国際現代音楽協会ISCMがコンサートを連続開催し、室内楽コンサートで日本の女性作曲家・外山道子の「やまとの声」の初演が行われている。
1937年万博の正式名称は「近代生活における芸術と技術の国際博覧会」であったことからも分かるように、この博覧会はテクノロジーに重点が置かれたもので、音楽面でも前衛的なイベントが行われた。特にセーヌの河辺で音と水と光を使って行われた「光の祭典」は、(美しい水)、(夢)、(幻想)など18のテーマをもつ新規音楽が奏でられた。byメイ
〈参考文献〉
吉野 亜湖 , 井戸 幸一(2025).近代万博と茶 世界が驚いた日本の「喫茶外交」史.淡交社
井上さつき.(2025).万博からみた音楽史.中央公論新社