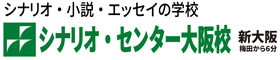「八百八橋にはドラマがある!」その31
~商人の町大阪にはこんな素敵な場所がいっぱい~
古代からつづく安堂寺
地名である安堂寺の名は諸説はあるものの、古代難波に住み着いた渡来人の安曇(あずみ)氏が訛って「あんどん」になったものとされています。付近にある船場を渥美と呼んだのも同様で、「あずみ」からきているそうです。また橋が架かるのは東横堀川ですが、その前身である安曇江(あずみのえ)を聖武天皇が船で渡ったという話が「続日本紀」に記されています。古代から水運が栄えていたこと場所だったのです。
江戸時代においては街道としても整備されています。玉造から生駒の奈良街道につながる道筋であり、早くから開けて商売も盛んでした。水運を利用して東には材木・竹などの取引が盛んだった材木浜、西には南船場がありました。金物問屋や砂糖商などの商売が盛んな土地柄になっていたのです。

伊勢神宮へつながる橋
安堂寺橋のもう一つの顔は、実は伊勢神宮へとつながる道になっているというです。商売の発展に伴って交通の要衝としても開けたことで、当時はここから伊勢へと旅立った人々も多かったと言われています。
大阪の安堂寺から、玉造~深江~生駒へと街道を歩いていく道中だったに違いありません。その証拠として、上方落語「東の旅」でも喜六と清八の二人連れの旅人が「安堂寺橋を東へ東へ」と旅立っていく姿が描かれています。当時のポピュラーなコースとして広まっていたからでしょう。

あの有名な落語にも登場
そんな安堂寺橋ですが、上記した「東の旅」以外の落語にも登場しています。その落語とは、あの「饅頭こわい」です。噺は人が集まって怖いもの自慢をする話ですが、話の中盤で登場するおやっさんが東横堀川の安堂寺橋の付近で幽霊に会ったと語るシーンがあります。幽霊に追いかけられて慌てて水に飛び込んで、起きたら夢だったという話です。
安堂寺橋が落語から続日本紀まで幅広く登場しているのも、古代から発展してきたこの場所だからこそであるとも言えるでしょう。いまはひっそりと佇む橋ですが、もしかすると意外な心霊スポットかもしれませんね。