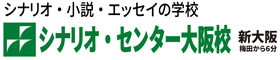俳句の季語は奇語ばかり?1
「亀鳴く」と「呼子鳥」 春の季語
「亀鳴く」は、「かめなく」で、雄亀が雌亀を慕って鳴く声が、春の夕暮れに聞こえてくるという季語だ。だが、亀は生物学的に鳴かないからファンタスティックな季語である。
由来は古く、鎌倉時代中期の公家・藤原為家が詠んだ「河ごしのみちのなかじのゆふやみになにぞときけばかめぞなくなり」(『夫木和歌抄』)から。ユーモアたっぷりの作だが、春の夕暮れのホンワカとした感じがうかがえる。
和歌から発した季語だという事実が驚きで、今では使われることは少ないだろう。
「呼子鳥」は「よぶこどり」と読むが、人を呼んでいるように鳴いていると感じられる春の鳥のことだ。
「万葉集」の春の雑歌にも詠まれていて歴史は古い。「貌鳥(かおどり)」や「花鳥(はなどり)」も同じ意味だ。
俳句に現れる鳥の名には、「郭公(かっこう)」や「時鳥(ほととぎす)」などがあるが、具体的には何という鳥か不明だ。
そこで講談社の『カラー版新日本大歳時記』をみてみると「……筒鳥(つつどり)、鵺(ぬえ)、鶯(うぐいす)……さらには猿とするなど諸説入り乱れている謎の鳥」と出てくる。
きっとキーキー鳴く猿の声を鳥と勘違いしたんだと考えると得心がいく。
だから其角も「むつかしや猿にしておけ呼子鳥」と詠んでいるではないか。byメイ